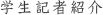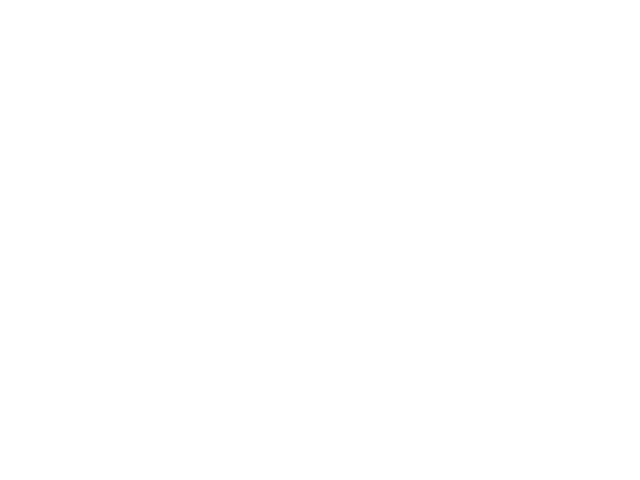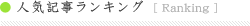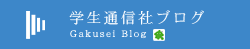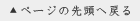生活習慣病の拡大や高齢化が進む日本。フィットネスクラブ運営やスポーツ用品販売を行うサップス(兵庫県芦屋市)は、地域社会のコミュニティーを築きながら人々の健康増進をサポートしている。中瀨敏和社長に起業のきっかけやスポーツクラブの現状、今後の展開を聞いた。――起業のきっかけは
姿勢が正しくなる靴を紹介する中瀨敏和社長
「起業する前にスイミングクラブの現場で水泳指導を行っていた。杖(つえ)をついてスイミングクラブに通う80歳の女性に水中歩行の指導をすると、3~6カ月後には杖を使わずクラブに通うことができた。指導者と利用者がともに感動体験を増やしていける企業をつくりたいと思った」
――どのように事業展開してきたのか
「フィットネスクラブ市場のシェアは、大手3~5社で5割程度、残りを中小が占める。なかには経営が難しく行き詰まっているところもある。例えばクラブ内で水着を販売するプロショップは、仕入れても売れないことで在庫を多くかかえ、利益が残らないのが現状だ」
「大手の場合は、多く仕入れても運営する他のクラブに商品を回したり、バーゲンを行ったりすることで在庫をなくすことができる。しかし、中小のフィットネスクラブは、多く仕入れても他の店舗に商品を回すことができないことから完売できずに在庫をつくってしまう」
――在庫リスクを受け持ち、中小フィットネスクラブが利益を生み出す仕組みを提供している
「他にも中古マシンの取り扱いを始めることで初期投資のコスト削減を可能にして地域のニーズに合ったフィットネスクラブ作りに貢献。物販からランニングコストの削減など運営ノウハウを中小のクラブに対して提供できるようになり、現在、関西を中心に150店舗以上と提携している」
――日本でスポーツジムに通う人は増えている
「20年前のアメリカのフィットネスクラブの参加率は、人口の10%で現在は16%に増加している。他国でも、スペインは16%、スウェーデンでは15%であることから、日本のフィットネス業界の参加率も7%には増えると期待されていた。しかし、日本のフィットネスクラブの参加率はこの20年間、3%台にとどまっており、業界全体としての大きな課題と考えている」
――戦略面での特徴は
「大手とは違うコンセプトを打ち出して、地域のフィットネスクラブへの参加率を上げることを考えた。今までのマシンを使う運動ではぎっくり腰や、肩の痛みなど体の不調を訴える人がいる。そこで、従来の筋肉を増強して発達させる動きから、姿勢の矯正や歩行など日常動作の動きを高めることに注目した。特に力を入れているのはウオーキングだ。正しい姿勢で歩くことで膝の痛みや腰痛、転倒を予防することができる」
「また、腰にセンサーを付けて歩くことで自分の歩行姿勢が正しいかが判断できる測定器『LegLOG』を使い、運営するフィットネスクラブで歩行指導を無料で行っている。そうすることで今まで運動に関心の薄かった層にも興味を持ってもらえるようになった」
――今後の展開は
「運動から地域のコミュニティーを支えたい。例えば正しい歩行指導ができる中高年者を養成し、新しい雇用の場を創出したい。また、ウオーキングを通して地域の高齢者の見守りや防犯など、さまざまな地域の問題解決につながるような健康コミュニティーを創出していくことにも力を注ぎたい。そして、愉しさと心地よさ、生きる喜びを伝えながら、社会に必要とされる企業でありたい」
(学生通信社 関西大学・喜多元哉)
※「フジサンケイ ビジネスアイ」2012.7.2(西日本版)掲載
- 介護食品の認知度向上へ インターン生の挑戦(2014.04.24)
- 「イコール」岡本真太郎代表に聞く(2013.10.24)
- 「ミュウシード」 河合德治社長に聞く(2013.05.24)
- 孤独死防ぐ、高齢者と若者をつなぐパッチワーク(2013.04.05)
- HPは制作より運用重視 ポテンシャルユナイテッド 平野孝幸社長(2013.01.14)
- 「サンフレックス」 宮井賢次社長に聞く(2012.11.08)
- 物語のあるデザイン クリエイターと語りあえるマーケット(2012.10.22)
- 国際交流も楽しめるショッピングサイト始動(2012.10.09)