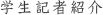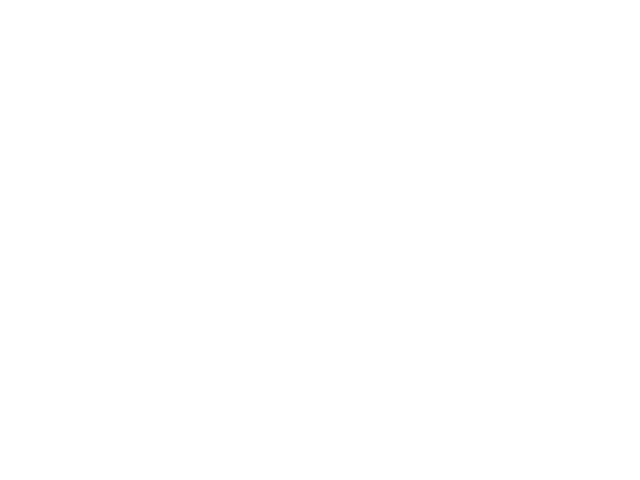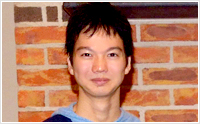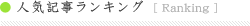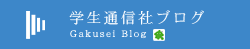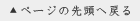学生がレーシングカーを開発・製作し、ものづくりの総合力を競う「第10回全日本学生フォーミュラ大会」が2012年9月、静岡県袋井市で開催された。同大会は03年から学生の「ものづくり育成の場」として開催され、今回は国内外合わせ82校のエントリーがあった。その中のひとつ同志社大学フォーミュラプロジェクト(DUFP)は総合成績3位を達成。これまで10位以内に入ったこともなかった、このチームがなぜ飛躍できたのか…。学生たちの取り組みを探った。DUFPは、自動車や、ものづくりに興味がある学生が集まり、第1回大会開催に合わせて結成されたチームだ。毎年総合成績10位以内をめざして、同大学京田辺校地で車両の開発や改良に取り組んできたが、これまで、その目標を達成できた年はなかった。
街で見かける車は、キーを差してひねるだけでエンジンがかかり走り出す。しかし自分たちで車を作ると、そのことがどれだけ凄いかが分かるという。設計を緻密に行わないと、製作した部品同士が接触したり走行中にボルトが折れたりすることがある。空気とガソリンの割合を適正に調整しないとエンジンが動かないなどといったトラブルも多発。緻密な設計やトラブルに対処する力はもちろん、スケジュール管理やチームワークが重要になる。
24人が所属するチームには技術部と、広報や会計などを担当する総務部がある。直接、製作に関わる技術部はフレーム、サスペンション、ブレーキ、エンジンなどを担当する6班で構成されている。昨年度まで、メンバーは自分の所属する班の仕事が済めば、他の班を手伝うことはなかったといい、他の班の役割や重要性を認識できず、自分の班の主張ばかりをしたため、けんかになることもあった。
これまでは車両のトラブルやチームの連携不足から、予定していた期日内に車両を完成させられたことがなかった。そのため、テスト走行の時間が短くなり、車両の調整を十分に行えず、大会本番中にもトラブルに見舞われた。この経験から、チームで車を作ること、先を見越して活動し車両完成までの期間を短縮することが自分たちの課題だとわかった。
12年度のチームリーダーの理工学部3年生、宮田哲次さん(22)はレーシングカーを作るためには、全員が心をひとつにして取りかかることが大切だと感じていた。課題を克服するために、メンバーそれぞれの認識にずれがないように何度も話し合った。気持ちの面で妥協することがないように、目標を以前より高い総合成績9位以内に設定した。その結果、一人一人に責任感が出てきたという。お互いに意思疎通を図れ、全体の工程がスムーズに動いたため、期日通りに完成させることができた。以前よりもテスト走行に時間を割け、車両の耐久性の向上、大会へ向けての準備、シミュレーションを十分にできた。
大会では、めざしてきた総合成績9位以内をはるかに上回る3位という結果を得た。上位校が耐久走行の競技で次々にリタイアしていくなか、常に安定した走りができたからだ。宮田さんは「大会中は きちんと走り切ることができるか少し心配だったが、やることはやったという自信の方が強かった」と話し、ものづくりは技術力だけでなく組織力も大切だと実感できたそうだ。「チームがひとつとなって動くことによって、単なる個々の足し算以上の力を得ることができた」と振り返る。同時に、世の中にあるものが壊れないように設計や加工ができていることの凄さも身に染みて感じたという。「ものづくりの現場へ入って行く責任を感じた。今後は社会に貢献できるようなエンジニアになれるよう勉学に励みたい」と宮田さんは話した。
〈取材後記〉
僕の夢は車の設計をすることで、現在機械システムの勉強をしています。また、昨年度までこのチームの一員でした。僕自身は、チーム内で人に自分の考えを分かりやすく伝えることができず、他のメンバーとの意思疎通ができていないことがありました。今回、目標を実際に達成したチームへの取材を通して、改めてチームとして動くことの大切さを学ぶことができました。僕は、車はチームが産み出した一人の子どものようだと感じています。この学生時代の経験を踏まえ、日本のものづくりを引っ張っていく存在になりたいです。最後に、このような感動を与えてくれたチームにひとこと「ありがとう」と言いたい。
- 「坂本設計技術開発研究所」坂本喜晴代表に聞く(2014.06.02)
- 【学生記者が行く】NPO法人「Co.to.hana」西川亮代表に聞く(2014.05.09)
- 「シンクスバンク」 谷口升太社長に聞く(2014.04.30)
- 大人は立ち入り禁止、小学生がつくるまち(2014.04.24)
- 神戸で10年続くチャリティー音楽祭、主催者に聞く震災への思い(2014.04.24)
- ANA、小児がん施設で模擬フライト(2014.04.24)
- 兵庫県の魅力を世界へ発信~安藤忠雄建築~(2013.04.27)
- 「東洋製鉄」の音頭良紀専務に聞く(2013.01.30)