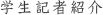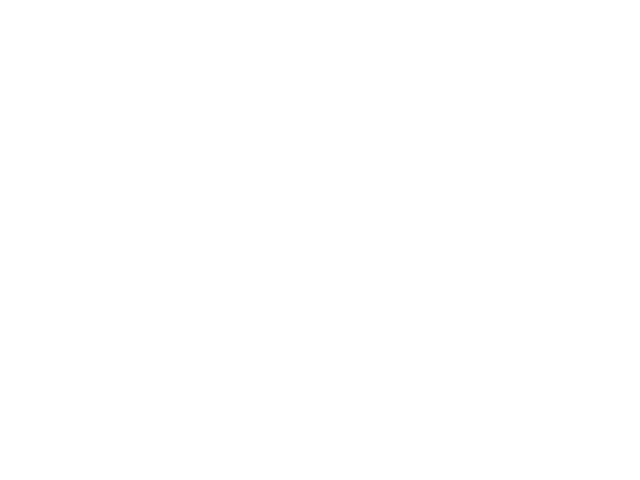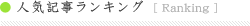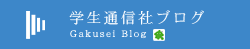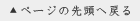リチウムイオン電池を搭載した小型の電気自動車「マイクロ・ビークル」。環境に優しく、高齢社会に適した未来の乗り物だ。この開発を支援するのがマイクロ・ビークル・ラボ(大阪市西区)。松尾博代表(52)は技術者と経営者の二足のわらじを履き、企業や大学と電気自動車の開発に取り組んでいる。
マイクロ・ビークルは排ガスを出さないため、ガソリン車に比べ環境に優しいと言われる。また、ガソリン車はエンジンが温まっていない状態で走ると窒素酸化物などを排出するため、短距離の移動は電気自動車の方が環境面で適している。最近はセブンーイレブン・ジャパン(東京都千代田区)が宅配サービスにトヨタのパーソナルモビリティ「コムス」を導入するなど徐々に普及し始めている。
松尾さんは京都工芸繊維大学で無機材料の分野を学び、1985年、宇部興産(山口県宇部市)に入社。窒化ケイ素というセラミックスの開発を担当したが、より最終製品に近い分野の研究をするため90年、大阪ガスの子会社・関西新技術研究所(京都市下京区)に転職。受託研究業を行う同社でリチウムイオン電池の研究を進めた。2002年、マイクロ・ビークルの開発をする企業や大学向けにリチウムイオン電池を販売する事業を立ち上げる話が持ち上がり、松尾さんは担当部長に任命されながら、事故が起きた場合の安全面への不安から04年末に事業が中止に。「一人でもその続きをやりたい」「マイクロ・ビークルを開発する人たちを支援したい」との思いで05年に独立し、マイクロ・ビークル・ラボを設立した。
現在、松尾さんは大学時代や企業に務めていたときのネットワークを生かし、依頼された案件に合わせてチームを組んで仕事に取り組んでいる。リチウムイオン電池を別の会社から仕入れて組電池にしたり、保護回路をつけたりして電気自動車の研究者や大型リチウムイオン電池を必要とする人に提供する。企業や大学から特殊大型リチウムイオン電池の設計や試作、実証テストなども請け負う。
松尾さんは「仕事をするうえで大切にしているのは、自社で全部やろうとせず技術を持っている人に依頼して作ってもらうこと。相手と親密に連絡を取り、お互いの技術を尊重し合うことも重要です」と語る。大企業と下請けのような関係ではなく、「お宅の技術のこの部分を生かしてほしい」「値段ではなく、技術で勝負しましょう」などと会話のキャッチボールを心がけ、対等な関係を築いているという。
マイクロ・ビークルの開発支援に長年かかわってきた松尾さんだが、「普及させるのは容易でない」と語る。ガソリン車に比べるとエネルギー密度が低く、同じ容量の燃料で比較すると10分の1ほどの距離しか走行できない。逆にガソリン車と同等の走行距離を確保するためにバッテリーを多く搭載すると、自動車の価格が現状の10倍にもなるからだ。また、街で走行する際は専用レーンの敷設も求められるという。
多くの壁が立ちはだかるなかでも事業を続ける理由はなにか。松尾さんは「技術者としての使命です。電気自動車は万能な自動車ではありませんが、今後ガソリンに依存しない社会になっていくことは確かで、そのために技術的な課題を克服しなければなりません。ガソリンと電池だけに依存するのではなく、太陽光や風力で発電した自然エネルギーを有効に使う方法を技術者や科学者は考えていかなければ」と話した。
〈取材後記〉
ここ数年、フリーランスやノマドワーカーと呼ばれる人が話題になっている。松尾さんも一人で会社を経営しており、それに近い働き方をしている。取材を通して、組織に縛られない働き方をするには経験と人間性が大事だと学んだ。松尾さんは前職時代に事業部長として予算を管理したり、部下をまとめたりした経験がある。また、マイクロ・ビークルへの熱い思いを持ち続け、実績を積み重ねて信頼を得てきた。だからこそ独立前に培った技術と人脈を生かして働くことができる。松尾さんのような働き方が広がることで、今までは日の目を見ずに消えていってしまった技術が、社会で生かされるようになればと思った。
- ミラノで「和」を発信、「旅芸人」の仕事の流儀(2014.04.24)
- 「庭とともに心豊かな暮らしを」 庭職人という生き方(2014.04.24)
- 関西のモノづくり魂、開発途上国へ(2014.04.24)
- 新しい制震技術で自然を感じる暮らしを――積水ハウスの「スローリビング」(2014.04.24)
- 【学生記者が行く】「ココウェル」水井裕社長に聞く(2014.04.22)
- 「人間愛」で社会に必要な企業へ 積水ハウス 02(2014.04.17)
- 「人間愛」で社会に必要な企業へ 積水ハウス(2014.04.17)
- 【学生記者が行く】「グローバルエンジニアリング」荒川健一社長に聞く(2014.04.17)