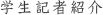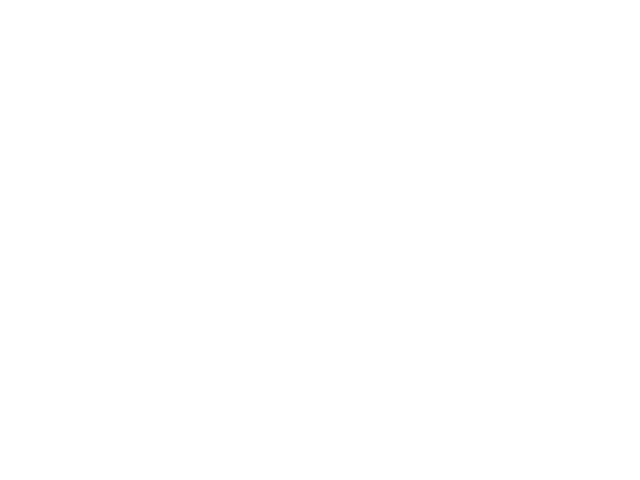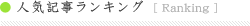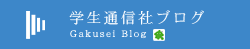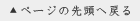学習塾KECゼミナール(奈良県生駒市)の「理科実験教室」が先月1日、同塾の学園前駅前教室(奈良市)で開かれた。小1から小5を対象とし、自発的な探究心と表現力の育成を目的としている。今回はキットを使って目に見えない電気をイメージしやすくすることで、楽しく発電の仕組みを学んだ。参加した11人の小学生は手回し発電機を使って豆電球と発光ダイオードを光らせ、自分たちの作った電気で車を走らせた。
手のひらサイズの発電機の中にはモーターが入っている。ハンドルを回すことでモーターを回転させ、電気を作る仕組みだ。子どもたちは発電機に豆電球と発光ダイオードをつなぎ、ハンドルを回した。
講師の横野健一さん(44)がハンドルの手ごたえについて尋ねると、子どもたちは口々に発光ダイオードの方が回しやすいと答えた。子どもたちは実験結果から、発光ダイオードは豆電球よりも使う電気が少ないという“結論”を導き出した。学んだことを身の回りの事例に例える場面では、横野さんの「発光ダイオードを使ったLEDは少ない電気で光るから熱くない」という説明には「だから蛍光灯は熱いの?」という質問もでた。
発電機を使って車を走らせる実験も行われた。ハンドルを逆に回すと車が反対に動いたことから、逆回転させることで、車に流れる電流が逆になることを考察。教室のなかで始まりから終わりまで子どもと横野さんとの間で活発なやりとりが飛び交っていた。
奈良県下の学習塾でいち早く「表現」の授業を導入したのがKECゼミナールだという。その成果をもとに始まったのが「実験教室」を開いてレポートを書かせる試み。今回の教室でも参加した児童たちは実験の経過を文章にまとめた。
8月に発表された平成24年度全国学力・学習状況調査の抽出調査結果は「観察・実験の結果などを整理・分析した上で、解釈・考察し、説明することなどに課題が見られる」と指摘している。横野さんは「レポートでは目に見えて分かる実験結果とそこから考えて分かることを意識的に分けて書いてもらっている。自分の思考の過程を記述することは、表現力を培う良い機会になる。表現力は中学での自由研究から社会人での企画書作りでも必要な力。レポートを通じて、小学生のうちから身につけていってほしい」と強調する。
参加した小学校5年生の西川大翔君は「豆電球と発光ダイオードの違いが分かって面白かった」と話す。横野さんは「興味を持つことで疑問が生まれる。勉強するなかでなぜ、どうしてと考えるのはとても大事。理科実験でそういう機会を与えたい。表現力までを培うことがKECゼミナールの特色。10年20年後も役立つ考える力と表現力を育成する一環としてこれからも理科実験を続けていきたい」と教室での成果を確信している。
<取材後記>
私の高校の化学教師はよく学習内容を「『混ぜるな危険』がなぜ危険なのか」といった身の回りの事象に捉えて説明してくれた。化学は難しかったが、今まで知らなかった身の回りの仕組みを知れるその授業が毎回楽しみだった。その化学教師はよく「化学は分かっていなくても生きていける。でも同じものを見てもその仕組みが見える人と見えない人がいるなかで、見える人になってほしい」と言っていた。理科を学習することは、世の中の違った見方を知ることだ。理科実験中の好奇心旺盛な子どもたちを見て、これからも身の回りのたくさんのなぜを考えて、新しい見方を知ってほしいと思った。
- 人との出会いで人生は変わる(2014.04.27)
- 動物病院の培養キッドで再生医療を動物にも(2014.04.25)
- 福祉を仕事に、2月に大阪で就職フェア(2014.04.25)
- 掃除でエコを実感(2014.04.25)
- 仕事場を遊び場に――俺らの夢工場(2014.04.25)
- 中小企業で連合し、モノづくりから価値づくり(2014.04.25)
- 【学生記者が行く】「福市」高津玉枝代表に聞く(2014.04.22)
- 【学生記者が行く】「アル・コネクションプロダクツ」中西理翔代表に聞く(2014.04.22)